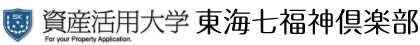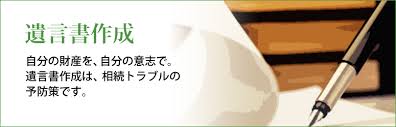『遺言の作成』
出口戦略は、不動産売却用語ですが
「どんな人生を送るか」という出口を
想定することにもつながります。
その想定することを文書に書きとめる
のが一つの表現としての「遺言」です。
「私にはまだ早い・・・・」
遺言書作成のご提案をする際に、
よく資産をお持ちの方がお話しになる
言葉です。
遺言の作成に適齢期はありません。
なぜなら、相続対策は「今」の対策
ではなく「将来の万が一」の備える
為に行うものだからです。
実際に、「あの時に遺言書を作成して
おいてよかった」というケースも
よくあります。
今社会問題になっている認知症など
意思能力がなくなると遺言書は作成
できません。
「思い立った時に作成する」ことが
大切です。
遺言書がなくて分割協議で揉めてしまう
と、以下のような不都合が生じます。
・被相続人名義の金融機関の口座が凍結
され、いつまでもお金が引き出せない
・不動産の名義変更ができず、不動産
収入は相続分で按分しなければ
ならない
・分割が終わるまで相続人全員の共有
財産となる為、有価証券などの処分
も出来ない
・相続税の計算上、各種の特例が使えず
割高になる。又農地の納税猶予や
物納も許可されない。
不都合なことも多く、遺言がないことに
よるマイナス面が非常に多いことが、
おわかり頂けると思います。
また、相続人の中に未成年者や成年後見
が必要な人がいる場合にも有効です。
遺言書の作成は、もちろん遺言者の遺志
で行うものです。しかし遺産の分け方に
よっては、相続税の税負担や納税資金の
確保に大きく影響します。
検討すべき主なポイントは次の通りです
・配偶者の税額軽減の適用
・小規模宅地の減額
・債務承継者
・農地の承継者(納税猶予適用の時)
・相続税の納税ができるかどうか
・付言事項により円満相続はどうか
など
信頼できる税理士さんか、専門の機関
などに相談することをおススメします。
最後に、税法上不利でも、「争族」を
避ける為に生前贈与をするのも、一つ
の方法かと思います。