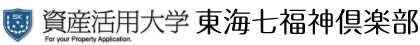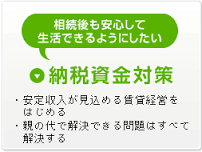『納税資金を貯める仕組みづくり』
〈減価償却以外の仕組み〉
相続税の納税資金は計画的に貯めること
が必要です。前々回に①減価償却の活用で
納税資金を貯めることを、お話ししましたが
それ以外の内容をご紹介します。
□減価償却費を多く計上できる
期間を活用(前々回お話し済み)
□小規模企業共済制度を活用
□生命保険の活用
□生前贈与
□不動産経営の法人化
□小規模企業共済制度の活用は、
大規模修繕費にも使えて、納税資金にも
活用できる制度です。
掻い摘んでご案内しますと、この共済制度は、
国が全額出資する独立行政法人、
中小企業基盤整備機構が運営していて安心です。
この制度には不動産賃貸業をされている方も
利用で、平成23年1月からは共同経営者も加入
できるようになりました。
掛け金は月額最高7万円で年間84万円です。
加入時に、支払った掛け金は全額所得控除を
することができます。又共済金の受給時において、
相続人が受け取った際
「500万円×法定相続人の数」まで非課税
になります。
□生命保険の活用は、相続人が受け取っても
「500万円×法定相続人の数」までは
相続税が非課税になる規定があります。
これは小規模企業共済の非課税枠とは
別枠ですから合わせて活用できます
もちろん現金がある方が納税金額に見合う
保険をかけて、納税対策を行うことも有効な
対策です
□生前贈与についてですが、親の蓄財をする
のではなく、子で資産を増やすことが相続対策の
基本です。
賃貸収入で得たお金を生前贈与で子に渡し
将来の相続税の納税資金として貯めて
おくようにします。
□不動産経営の法人化については、
不動産経営の法人化により、子が給与を受け取って
納税資金を貯めておく方法も有効です。
ここでは、5つの納税資金対策をまずご紹介
しましたが、生命保険、生前贈与、法人化に
つきましては、今後のメルマガで、お話しして
いきます。